回り道も含め、後退知らず
取材・文 | 久保田千史 | 2012年4月
main photo | ©Sylvia Steinhäuser
――Raster-Notonからお声がかかった経緯について教えてください。
「ベルリンの小さいお店でDJをやった時に、わたしがかけた曲を気に入ってくれたお客さんがいて。翌週にDenseっていうレコード・ショップでインストア・ライヴをやったんですけど、その子がそこにFrank(Bretschneider)を連れてきてくれたんです。その時Frankとは初対面だったんですけど、“すごく良かった”って言ってくれて、それから全部のライヴに来てくれるようになって。毎回褒めてくれるんですよ。そのあたりから、Olaf(Bender)やRobert Lippokともばったり会うようになって、知らないうちに坂本龍一さんがGROOPIESをCarsten(Nicolai)におすすめしてくださったりで、なんか自然に。こんなお話で大丈夫ですか(笑)?」
――はい(笑)。
「それから特に何もなく、わたしも自分の音楽活動をしていたんですけど、ある時期、ケムニッツにいることが多かったOlafがしょっちゅうベルリンに来るようになって。何度かばったり会ったときに“そういえばKyokaの音をまだ聴いたことがないから、聴かせて”って言われたんですね。でも、あまりにRaster-Notonとは違うし、とは言えすでに大ファンでもあったので、しなっと逃げ腰になってて。なかなか聴かせられませんでした」
――毎回断ってたんですか(笑)?
「違い過ぎてシラケたら嫌だなと思って(笑)。恥ずかしかったのかな。なんとなく。Raster-Notonて、ばりばりストイックじゃないですか。わたしはそんなにストイックでもないから、彼らから見たらバカに見えるんじゃないかなって思って」

――Kyokaさんもストイックに見えますよ。
「そうですか?でもOlafは多分好きじゃないだろうと思ったんですよ。せっかく仲良くなったのに、曲を聴かせたこと友情が崩れる気がしてしまって(笑)。でもある日、腹をくくって聴いてもらったんですね。3rd EP(『3ufunfunfufu』)の音源で、1曲目、2曲目は“なるほどね”っていう感じで頷いてたんですけど、3曲目、「pc125bpm」っていう曲で反応して、“これCarstenに送って” ってCarstenの連絡先を教えられたんです。でもまだ3rdのリリース前で、onpa)))))からリリースする用に作った曲だったから、それを勝手に送るのはどうなんだろう?ってモジャモジャしていて、結局あやふやになったんですね。でもRaster-Notonが、レーベルのカラーに合っていて1人でやれる女性アーティストを探してたことは確かで。その後色々あって、また1年後に音源を渡すことになったんです。そこで“次のリリースはKyokaでいいと思う”ってお返事をいただいて、またそこから色々あって今に至ります」
――Raster-Notonから実際リリースされてみて、いかがでしたか?
「リリースが決まって、曲を更に仕上げていく時点ですごく緊張しました。Raster-Notonて、ヨーロッパでも当然の如き人気を誇ってるレーベルだから。仕上がってから1回目のライヴを東京でやったんですけど、リリースの音源を使った初ライヴでスベりたくないと思って、それもすごい緊張して。ライヴ前日は全然寝られなくてスベる夢ばっかり観てたくらい(笑)。以前に比べて変な責任感を感じますね(笑)」
――それは、Raster-Notonの看板が重いってことなんでしょうか。あまり看板を気にするタイプじゃないと思ってました(笑)。
「なんだろ、看板ていうか、等身大より大きめの負荷を自分に常に背負わせるのがわたしで、“あー、またうまく背負っちゃった”と。onpa)))))のときはすごく自由にやらせていただいてたので。“音質もビートも何にも考えなくていいよ”って(笑)。それはすごく楽しかったんですけど、EP3枚それで遊ぶと、さすがに世間知らずになってきちゃって。外の世界に行ってみようと。1枚目を作ってる頃からonpa)))))の羽生(和仁)さんに、たぶん3枚出したらわたし、外の世界にも出たがると思うんでって話していたので、快く送り出してくれて」
――そうですね、これまでの作品から更に一皮剥けましたよね。
「そうそう。3枚目までの、あのクチャっとした無邪気さがなければ、ここまで大人になれなかったんですよ、わたし(笑)。最初からこれをやっていたら、先が続かなかったと思います。onpa)))))やGROOPIESがあったから今も自信が持てるんですよね」
――いつもアートワークにも拘っていらっしゃる感があるのですが、今回のミニマルなジャケットは寂しく思っていませんか?
「これも絶対的に可愛いですよ!」
――今後アルバムもRaster-Notonから出るとなると、やっぱりグレースケール基調のミニマルなジャケットになると思うんですけど。
「えー。完璧楽しみにしてました!わたし、周りから見るとどんどん変わる人に見えるのかもですが、わたしの中では一貫して理想に近づいてるんです。経緯や回り道も含めて、後退知らずなんですよ。だから楽しみだなーって思って、何にも気にしてなかったです」
――レーベルメイトになった面々の中では、シンパシーを感じる人っていますか?結構みんなKyokaさんとは音が違うと思うんですけど。
「シンパシーというか、人間的にも音的にもフランクはずば抜けて親友!色んな話をしますが、理にかなう話ができる。あと、先日ベルリンの“Transmediale”のライヴで一緒だったMark Fellがすごく良くて。最近はMark Fellばかり聴いてますね、レーベルの人だと。Mika Vainio(PAN SONIC)は剥き出しのケーブルを触ったりしながらライヴをやるんですけど、あれはすごいシンパシー感じます。彼のライヴを観ると対抗意識が燃える(笑)。あと、今回Atom™がリミックスをしてくれてるんですけど、彼にリミックスを頼んだ理由をCarstenは“Kyokaとユーモアの方向性が似ている気がするから”って言ってるんです。Atom™もキッチィな時とストイックな時とあるから、分かる気もします」
――このリミックスの仕上がりはどう思われているんですか?
「なんかノリノリで新しかったです。わたしの音源の素材でもこうなるんだって思いました(笑)。びっくりした」
――その原曲「HADue」は、Raster-Notonリリースのきっかけのひとつになった「pc125bpm」とすごく連続性を感じたんです。意識して作られたところはあるんでしょうか。
「意識はしてないです。そういう部分に関してわたし自身は客観的じゃなくて。わたしがランダムに作ったものを、周りの人がわたしの抽出部分を選んでくれるんです。そういうところはありがたく参考にさせていただいてます」
――どちらもハンマービート色ありますし、Raster-Notonはそこに反応したのかもしれないですね。ドイツ人好みだったというか(笑)。
「そうなんですかね?FlankがCarstenとOlafにわたしのことを初めて紹介してくれた時、音がダイレクト、ダイレクトって言ってたんですよね(笑)。そうなのかな?って思ったけど、直球も悪くない響きだなって」

――直球、かっこいいですね(笑)。あと、エディットの幅が大きくなった気がするんですよね。ロックっぽく言えばリフがビッグになったっていうか。そこもダイレクトかつ洗練された印象に繋がってるのかなって思います。
「そういえばそうですね……」
――洗練されても、引き続きワイルドさを感じさせるところもおもしろいです。
「さすがFrankプロデュースですよね(笑)」
――Frankさんとの作業は、みっちりやったんですか?
「すごかったですよ。やってよかったです。わたし今までずっと1人で独学でやっていて、誰かに何かを習うってことが一切なくて。でも毎回自分なりに宿題を見つけて曲を作ってきたんです。だからちょっと煮詰まってたんですね。でもFrankとの作業で、これからもやることがいっぱいあるなって気付くことができて」
――具体的にどんな作業だったんでしょう。
「パソコンの埃を取ったり、ハードディスクの要領を空けたり(笑)。パソコンの周りが散らかってるだけで怒られるんですよ(笑)。“君の人生を支える大事な物に、何で埃を付けるんだ”って(笑)」
――几帳面そうな方ですもんね(笑)
「そうそう(笑)。実際は色々と細かいところをいじったりはしていたんですけど、この作業でそんなに変わらないだろ、くらいに思ってたんです。でも仕上がりを聴いたら格段に良くなっていて。Frankが埃を“フッ”てしただけなのに(笑)。見てない時に何かやった?って聞いたら“何もしてない”って。マジック(笑)?」
――その“埃取りマジック”みたいなお話って、すごくアナクロっていうか、アナログじゃないですか。そういうところもKyokaさんの作風と繋がってる感じがします。
「ああ~。アナログですよね、わたし」

――棚のコーナー的にはエレクトロニック・ミュージックだけど、あまりそういう雰囲気がないっていうか。
「そうですね、自分でもそう思います。多分、パソコンを使っているだけで、やってることはアナログなんですよね。元々、音に魅力を感じたのが相当小さい時で。3、4歳の頃に、カセットテープ・レコーダーのヘッドに色んなものをくっつけて遊んていたら、親がテレコを4台も買ってくれて(笑)。それでマルチトラック・レコーディングを始めたんです(笑)。先日agraphくんに“2台でいいじゃん”て指摘されましたけど(笑)。テレコは基本的なわたしのおもちゃです。ちょっとだけズラして再生するとエコーがかかるのを初めて発見したときの感動とか(笑)。その延長で今もやってるから、たぶん波形もテレコと変わらないんですよ」
――ライヴではCHORO CLUBの沢田穰治さんがベースを弾いていらっしゃいますよね。しかもちゃんとアンサンブルを感じるライヴで。そういうところもアナログっぽい印象を強くしていると思います。アンサンブルは意識して作っていらっしゃるんですか?
「それはたぶん、沢田さんの手腕ですね(笑)。沢田さんの曲に対する理解力ってすごくて」
――沢田さんとはどういう経緯で?
「いつの間にか知り合いになっていたんです(笑)。東京に居た頃、沢田さんがわたしの家から徒歩5分のところに住んでいたことがあって、よく遊びでセッションをするようになったんですよ。なんとなく三味線をまだ手元に持ってたから、持って遊びに行って、沢田さんのベースやギターとぐるぐる交代して遊んでいて。とりあえず何かできますね、っていうお話をしていたんですけど、それから10年くらい経ってしまって。一緒にリリースしたいってずっと言ってくださってたので、そろそろ何かやりますか、ということで。とりあえず、しばらくはお互いのライヴで、入れられそうなときに入れるという感じで模索中なんです」
――良いコンビですよね。
「そうですか?よかったです。わたしベースの音が大好きで。ベースの人って注目しちゃうんですよ」
――Mike Watt(THE MINUTEMEN, THE STOOGES)とか。
「そうそうそう」
――Mikeさんはどんな風に出合ったんですか?
「ある日、ロンドンタイムズの人からメールがいきなり来たんです。知らない人だったんですけど、“Mike WattのPodcastでKyokaの曲がたくさんかかってるけど、何であんなにプッシュされてるんだ”って聞かれて。知らないって答えたんですよ(笑)。そしたら、逆にMikeの連絡先を教えてくれて。“こういう人だよ”って。でもどうしたら良いか分からなくて、ありがとうとだけ連絡したら、”Kyokaの曲いつもかけてるんだよ”ってお返事をくれて。“Kyokaの作る曲は何でもベース入れるよ”って。Mikeも含め、なぜかわたし、バンドマンの友達がすごく多いんです(笑)」
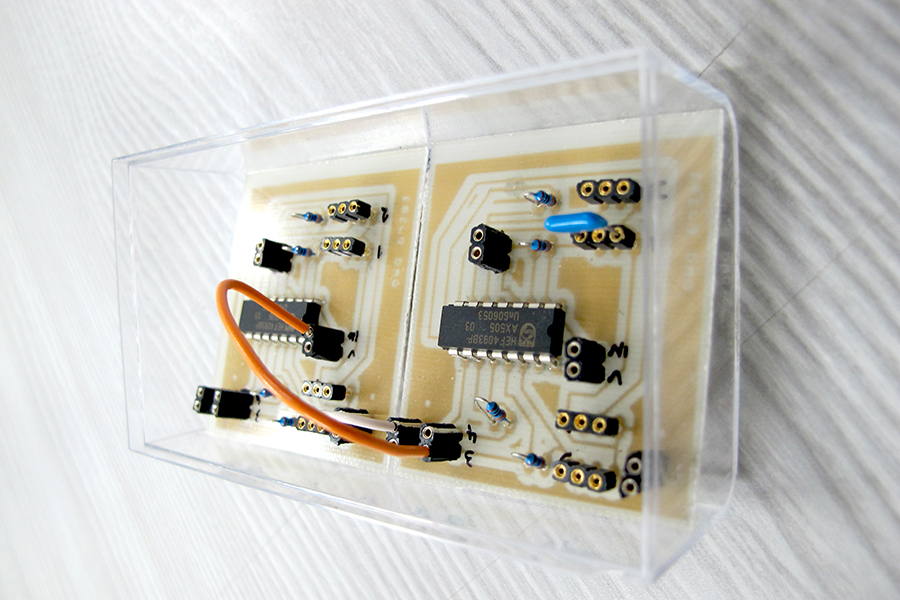
――へえ~!バンドマンを引き寄せる磁場か何かがあるんでしょうか(笑)。Kyokaさんの楽曲は、独りでバンドをやってるみたいに聴こえるからかもしれませんね。“エレクトロニカを作ろう”としている音楽とは違って。
「そうそう、onpa)))))から1stを出す時も“パソコン使ってるけどバンドマンだよねって”言われて、まぁ間(あいだ)かもね、とは思ったんですよ。確かに、エレクトロニカの人って“エレクトロニカ”みたいかも。みんなじゃないけど、そういうのは馴染めないです」
――黒電話666さんやASUNAさんといった方たちとも共演されていますし、所謂“エレクトロニカ”の括りっていう感じは全くないです。
「そうですね。トクマルシューゴさんとかも近い匂いを感じるかも。先日はsoup(東京・落合)で、sawakoさん、cokiyuさん、34423ちゃんと女子4人だけでライヴをやったんですけど、その時も誰も“エレクトロニカ”っぽくなくて、おもしろかったです」
――女子と言えば今回、“Raster-Noton初の女性アーティスト”っていうのがひとつ大きなキャッチになってますよね。女性であることってどういう意味を持つんでしょう。パソコンでの音楽制作は所謂バンドマン的な方法論と違って、身体的な制約は少ないでしょうし。
「先日ちょうどドイツの友人と話していたんですけど、彼が最近まで通っていた大学では、プログラミングの授業になるとセメスター毎に女子が減って、最後誰も来なくなっちゃうそうなんです。インターナショナルな大学なんですけど、国籍に限らず、女の人はプログラミングが苦手みたいなんですよね。煮詰まっちゃうんですかねえ。プログラミングにもいくつか種類があって、ことに論理的なものほど脱落する人が多いらしいです。2nd EPを出した時に、坂本龍一さんが“女の人は計算が苦手なイメージがあるけど、Kyokaちゃんはなんでできるんだろう”みたいなコメントをくれたんですけど、実はわたし計算してなくて。みんな細かい調整をする時に、多分数値を入力してるんですけど、わたしはディスプレイをちょっと倒して見えないようにして、マウスだけ使って空気を見て調整してるんです。感覚でやってるんですね。最近たまに電卓を使うようになったけど(笑)。でも基本的に、ディスプレイを観ていると数字に惑わされちゃうんですよ。Frankのスパルタ教育を受けてからは、それをやった上で、最後に小数点を電卓で計算して波の大きさなんかを作ってます」

――今回の教授のコメントは、“どういう音楽を聴いてきたら、こういうものを作る女性になっちゃうんだろう?”っていうものですけど、実際どんな音楽を聴いてきたんですか?
「あんまり聴いてこなかったんです……。教授の作品は聴いてますよ(笑)。“音楽”や“曲”というよりも、“音”や“響き”を尊重していて。人生で何度か“曲”だけ聴いてすごく良いって思ったことはあったんですけど、ある日作った本人に会ったら、人間性が好きになれなくて……。それ以来、仲が良い人が作ってる曲とか聴かせてくれる曲以外は信じられなくなってしまったっていうのはありますね(笑)。自分でピアノの鍵盤を叩いてみたり、カセットで遊んだり。あとラジオの“ブババー”にハマったり。あれ絶対ハマるじゃないですか(笑)。わたし実家が金沢で、日本海側だから、韓国系の音が入ってくるんですよ。そういう変わった感じの、“音”や“物”に注目してきたんですよね。あとバレエとかオーケストラの公演が金沢に来ると、親がよく連れて行ってくれて。でも曲はほとんど聴いてなくて、特定の響き、瞬間ばかりを気にしていたんです。音の部分部分は聴いてるんですけど、“曲”ってあまり聴いてなくて。親がピアノのレッスンを受けさせてくれたこともあったんですけど、バイエルから始めると、鍵盤の真ん中を使わなきゃいけないじゃないですか。でも真ん中の音が好きじゃなくて(笑)。今は好きなんですけど、その頃は。メロディに込めるっていう感じも好きじゃなくて、興味がなくなってしまったり。親はわたしがいつもあんまり1人でピアノを弾いてるから、好きなんだと思ったみたいなんですけどね(笑)。その後、なぜかは忘れたんですけど、親が三味線をわたしと一緒に練習し始めて。津軽三味線だから結構激しくバチバチやるんですけど、ビーンと来る音が良い突き抜け方していて、このアドレナリン!と思ったり(笑)」
――(笑)。その時点でもう1st EPと直結している感じがしますね。GROOPIESのときは更にアグレッシヴでしたし。
「ですよね(笑)」
――Kyokaさんの楽曲は一貫してビーティではあると思うんですけど、そういう作風になるきっかけみたいなものはあったんでしょうか。昔からテクノを聴いてたというわけではなさそうですよね。
「全然聴いてないですね。ただ、昔から踊ってる人を見るのが好きで(笑)。スペインにも行っていたことがあるんですけど、スペインの人ってすごい踊るし、アメリカの人もすごい踊る。衝撃だったのが、仲良かったブラジル人の友達のおばあちゃん。100歳超えたヨボヨボのおばあちゃんで、ずーっと座ってるだけなんですけど、嬉しくなると、ちょっと、こう、揺れるんですよ(笑)。それが素敵!と思って。それ以来、踊ってる人を見ると嬉しくなるんです」





