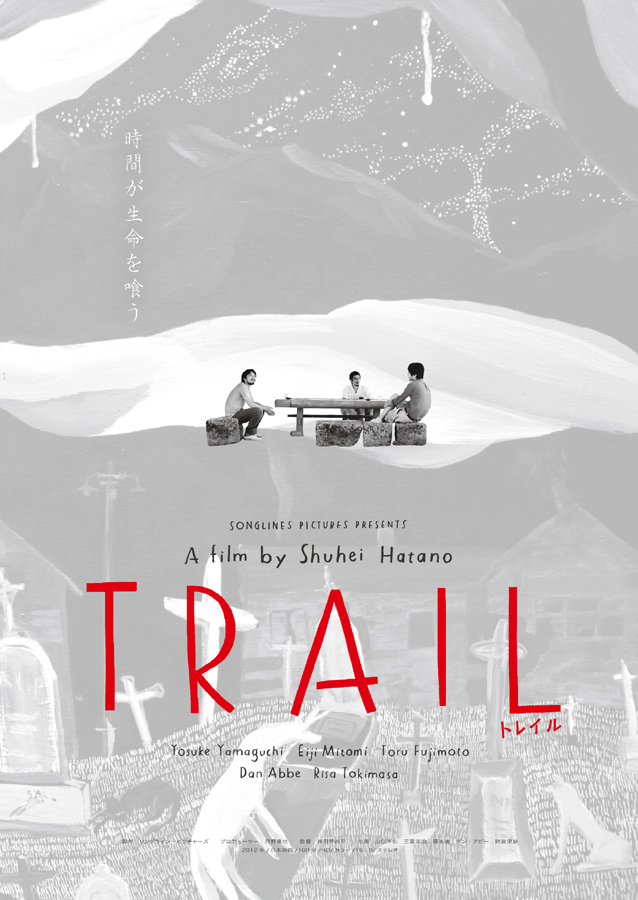“24時間自分” の絶対的不自由
※本稿には映画『TRAIL』のネタバレが多く含まれています。
取材・文 | 久保田千史 | 2013年6月
――映像作品はいつ頃から作られていたのでしょうか。
「出身が鳥取県の倉吉っていうところなんですけど、高校を出てから東京に出てきて、一浪して国分寺で予備校に通って、上野毛にある大学の映像学科に入ったんですよ。そこで映像の勉強をして」
――学校で勉強されていたんですね。
「そうですね。でも映像学科とは言っても、小説を書く人がいれば、ダンスや演劇やる人もいたり、現代アート寄りの人もいたりで、まあ基本何か表現すれば良い、みたいなところで。映像の機材は一応揃ってるんですけど。8mmとか16mmとか、フィルムが使えて。ちょうどメディア・アートみたいなものが出てきた時代だったんですけど、俺の通っていたところは元々夜間だったということもあってか、ちょっと雰囲気も暗くて、アングラっぽかったんですよ。だから先生も、実験映画の人が多くて。映画の技術とか映画史とかよりも“表現とは何か”みたいな授業が多かったんですよね。そこで実験映画とか、個人映画みたいな、所謂商業映画ではないものを知って」
――卒業してからは?
「渋谷の映画館で映写技師のバイトをしていました。藤本(徹)くんとはそこで知り合いました。彼が受付をやっていたんですよ。当時の彼は髪が長くて、ほっそいズボンでヘナヘナしてて、ちょっとトガった感じだったんですけど。Bobby Gillespie(THE JESUS AND MARY CHAIN~PRIMAL SCREAM)みたいな(笑)。でも好きな音楽も近かったりで話が合って、仲良くなって」
――彼はその頃から詩を書かれていたのですか?
「彼は最初、音楽をやっていたんですけど、曲に言葉を載せるっていうのができなかったらしくて。どうしても言葉先行になっちゃうみたいなんですよ。だったら言葉だけにしたほうが良いと思って、という話はチラっと聞いてます」
――就職は考えていなかったのでしょうか。
「しぶとく就職せずにがんばろうと思って(笑)、色んなバイトをしていました」
――あえてそうしてたんですか?
「なんでだろう(笑)。俺の通っていた学科の就職率がとにかく低かったんですよ。みんな就職活動なんかしていなくて。たぶん先のことなんか考えてなくて、そういうところに逃げてるだけだと思うんですけど(笑)。それで色んなバイトを転々とをして。まあ今もバイトもしてるんですけど」
――映画の制作は継続されていたのでしょうか。
「そうですね。ずっと自主制作で。まあ今回もほとんど自主制作なんですけど。短編を撮ったり、ライヴの映像を撮ったり。別に“やらなきゃ”っていう感じでもなく。撮るのを止めるとか止めないの問題じゃなくて、何かにつけ映画のことを考えちゃうんですよ。だからまあ、短編は結構作っていて」
――現在観られる作品は、YouTubeでも公開されている“Night People”シリーズや、テニスコーツとJad Fairのツアー・ドキュメンタリー『Enjoy Your Life』とか、音楽に関係したものが多いですよね。映画への入り口として、音楽の影響が大きかったとか?
「そんなことはないです。音楽はすごく好きだから、自然とかな。でも、音楽の人たちって、なにかとみんな繋がってるじゃないですか。ツアーが組めるくらいに。俺はそれがすごいな、と思って。映画ではそういうことがないような気がしてたんです」
――たしかにそういうイメージないですね。
「ね。なんか映画ってもっと、変な言い方だけど、バチバチしてるっていうか(笑)。そういう感じがちょっとしていて。俺が知らなくて、そこに居ないだけで、そんなことないのかもしれないですけど。音楽の人が、次は姫路でライヴ、じゃあ今度名古屋ね、みたいな感じで動けるのが羨ましくて。映画もそういう感じで作っていけたらなあ、って考えていたんです」
――バンドみたいな感じで。
「そうそう。バンドワゴンじゃないけど、そういうのに憧れて」
――今回の映画の構想はいつ頃から?
「アイディアというか、核みたいなもの自体はずっと昔からあったんです。たまたま鳥取の知り合いが、鳥取力創造運動支援補助金ていう県の助成金のことを教えてくれて。“鳥取力”をアピールできれば良いっていうアバウトな感じなんですけど(笑)。審査はなかなか厳しくて。それに通ってある程度予算に目処が付いたから、そろそろ長篇というものを作ってみようと」
――審査ではどんなプレゼンをされたんですか?
「まあ、鳥取で撮ろうとは思っていたんですよ。別に選んでというわけではなくて、鳥取じゃなくても撮れたとは思うんです。自主制作なんていうのは、誰に頼まれるでもなく撮るわけじゃないですか(笑)。スポンサーがいるわけでもないし。だから結局自分の中にあるものを重視して」
――原風景というか。
「そうですね。そういうところからアイディアが出てくるから、どちらかというとすでに決まっているという感じで。ちょうどその助成があるというので、まあ結構無理矢理な理由付けをして。よく“映画で町興し”みたいな話ってあると思うんですけど、あれって本末転倒じゃないですか。映画が良ければこそ、その土地に行った時に思いが広がるわけで。全然大したことない風景だったとしても。アピールしたい観光名所をネタに映画作っても意味がないと思うんですよ。そういうのでオッケーなのって寅さんくらいじゃないですか?なんとなく(笑)」
――寅さんは別格(笑)。
「そうそう(笑)。だから有形文化とかよりも無形文化、まあ民話だったり、生活だったり、そういうものをテーマにして映画を作りたい、というようなことはプレゼンで言いました。 “富士山”みたいなキャッチーさはないけど、全国で上映して鳥取を発信できます、ということで。実際そっちのほうが届くような気がするし。大変だとは思うけど」
――鳥取を盛り上げたいっていう気持ちから撮ろうと思ったわけでは全然ないんですよね。
「全然ないですね。やりたいことさえ出来れば、場所は結構どこでも良いと思うんですよ。例えば(ロベルト・)ロッセリーニの『イタリア旅行』なんかは観光名所がバンバン出てくるんです。でも主人公夫婦の関係がメインだから、そこさえしっかりしていれば何が出てきても成り立つんですよ。最後2人が抱き合った瞬間に、あー、よかった……って思えるわけです。何故抱き合ったのか理由は分からないんですけど(笑)。だから別に鳥取だろうが、立川だろうが、撮れるとは思うんですよね」
――でもやはり鳥取が撮り易かったということですよね。
「そうですね。土地を知っているっていうのは、やっぱり大きかったです」
――それは民話や生活に関して?
「はい。今回は人形峠っていうところの民話を入れてるんですけど、それは元々入れたかったものなんですよね」
――その民話は実際に伝えられているんですか?
「そうなんですよ。岡山県との境にある峠で、子供の頃から変な名前だな、って思っていたんですよ。昔々、巨大な蜘蛛が出て、旅人なんかが襲われていたんですね。それを退治するために人形を置いて、蜘蛛が人間だと思って食おうとしたところを、弓か何かで殺した、っていう伝説が残っていて。なんか割とグロテスクな内容の民話が、日常生活の中に名前として残っているということに違和感があったんです。でも色々調べてみると、そういう土地って全国各地にあるんですよね。それがすごく面白くて。いつか何かの形で映画にしたいなと思っていたんです」
――現代の生活と、民話とのギャップみたいなものが映画の核になるような感じだったのでしょうか。
「それは少し違って、言ってしまうのはアレかもしれないんですけど、この映画で俺が描きたかったのは、メインの3人でも、森でもなくて、抽象的ですけど“時間”なんですね。短編を撮っていた頃から時間を描きたいってずっと思ってるんですよ。時間を描くのは当然だろ、って感じですけど(笑)」
――まあ、経過という意味で言えば……。
「そうそう。でもこの映画を作るにあたって“時間を描く”っていうことだけがあって。そのひとつのモチーフ、過去から現在に続いている、繋がっているものとして民話を入れてみたんです。本当にあったかどうかも判らないくらい昔のものが、今に繋がっているっていうことを知ると、過去に襲われている感覚になるんですよ。主人公を3人の芸術家にしたのも同じような理由で。例えば、絵だと描いてた時間がそのまま定着するわけじゃないですか。時間を感じ易いんですよね。それこそゴッホみたいな、教科書でしか見たことがないような絵を生で見ると、内容どうこうよりも、まあ筆のタッチとか、100年前の人がここを筆で触ってたんだな、っていうのが直に伝わるじゃないですか。絵ってそういう力があると思うんですよ。博物館的な、古代の土器と同じような感覚というか」
――では3人の芸術家は経過を描けるような芸術家でなければダメだったっていうことですよね。写真家とかではなくて。
「どうなんだろう。でも写真家は想定していなかったですね。画家2人、詩人1人で最初考えてたんですよ。ただ2人目の画家がなかなか見つからなくて。どう違う人物を見つければいいのかで悩んで」
――なぜ画家が2人必要だったのでしょうか。
「それも元々、鳥取に実在した芸術団体をモチーフにしているからなんですよ。それをそのまま描くんじゃなくて、半分事実、半分フィクションみたいな感じで描けたらな、って最初は考えていたんですね。例えば民話って、事実をディフォルメして長持ちさせるということかな、って思うんです。劣化した事実を、フィクションで補完するというか。困難な峠越えを大蜘蛛で表したりね。そういう方法の方が核が抽出されて伝わり易くなることがあるんじゃないかと思っていて。芸術団体もそうやって描こうと思っていたんですけど、だんだん縛られる感じで重荷になってきて。それより、魅力的な主演3人をそのまま撮ったほうがいいや、っていう気持ちになってきたんです」
――2人目の画家ではなく、音楽家に落ち着いたのは?
「ふと、画家に拘らず音楽だったら誰だろう、って考えた時に浮かんだのが三富さんだったんです。以前SEPTIMAで演奏してくれたことがあったんですけど、音楽をちゃんと座って聴いてはいなかったんですよ。外でバーベキュー用の炭に火を熾したりしていて(笑)。その時のことをすごく思い出して。三富さんの音楽って、空気を思い出す雰囲気なんですよね。音楽自体も含めて“その時の音楽”みたいな感じがあって。フラッシュバックする記憶って“時間”に通じるな、と思ったんです。三富さんとはほとんど喋ったことがなかったんですけど(笑)、声を掛けたら快諾してくれて」
――藤本さんはそれまでにお付き合いがあったわけですけど、山口さんはどうしてオファーすることになったのでしょう。
「山口さんは、オファーするまでに2度くらいしかお会いしてないんですよ。最初はJad Fairのライヴの時に紹介されて、絵をチラっと見せてもらったくらい。その後、友達が住んでいた平屋が取り壊されることになって、そこに皆で絵を描こうっていう話になったんですけど、山口さんに声を掛けてみたら来てくれて。当日絵を描いているところを撮ってたいたら、魅力的だったんですね。映画での姿が浮かんだので、急に呼んで口説き落としたんです。山口さんの方も大蜘蛛の話に釣られたらしくて乗ってきて(笑)。藤本くんは、俺がずっと映画撮ってるからっていうのも少しあったんじゃないかな。すぐに引き受けてくれて」
――詩人を使っての時間の表現はどう考えていたのでしょうか。終盤に詩を読むシーンが存在しますが、作中ではかなり異色に感じました。単純に芸術家団体プロットの名残ということなのでしょうか。
「それもあるんですけど、“言葉”と“絵”と“音”は全部カブってないし、全部足したら“映画”になるっていうのが良いな、って思ったんですよね。“時間”の表し方に関しては、詩って一言で世界が立つ感じがするじゃないですか。そういう意味で写真に近いのかな。時間が蓄積していく感じで作っていくと、どうしても絵がメインの尺が長いカットになっちゃうんですよ。だから詩を読むシーンで、瞬間で世界を切り取るようにしたかったんです」
――あのシーンに収斂していくっていうか。
「そうなんですよね。自分でも色が違うかな、って言う気はしてるですよね。イメージが足されていく感じが」
――所謂“映画的”ということですか。
「そうです」
――最後にそうなることによって、良い意味でのキャッチーさが出ているんじゃないかと思うんですけど。説明的というか。
「うん。そういう風にはなるんだな、とは思いました。後半が前半を縁取るというか。そういう意図があるようにはしました。実はこの映画、編集が何パターンかあって、最初の段階では全体的に割と“映画的”だったんです。でもそれをプロデューサーに見せたら“こういう映画だったっけ?”って言われたんですよ。編集していくにつれて“生”の感じがなくなっていくのを俺も感じてたから、バレたか!っていう気持ちになって。そこから粗編に近いものに戻していったんです」
――では、後半の“映画的”な展開は、本来求めていたものとは違う?
「そこは今でも、たぶん今後作る上でも、難しいところで。この映画を作り始める時に、“時間”を描きたいって内容的な部分とは別に、“自分の思い通りにならない制作がしたい”っていう気持ちがあったんですね。考えていたことを超えていくというか。無我で映画を作りたかったんです。例えば音楽の人って、ライヴだと特にそうなんですけど、演奏したり、歌ったりしている瞬間は頭からっぽなんじゃないかって観ていて思うんですよ。そういうことがしたいな、と思って。映画って割と、緻密に計算されて構築したもの、っていうイメージがあると思うんですよね。この映画観た人にも“シナリオは?”って聞かれることがあるんですけど、何でそんなこと聞くの?って思っちゃって(笑)。音楽をやっている人に“楽譜は?”って聞かないじゃないですか。それくらい映画って、シナリオがあって、役者が演じて、監督がそれをコントロールする、っていう印象が強いんだろうな、って思ったんですよ。“映画観”ていうか。上映したときも“こんなの映画じゃない”って言われたりもしたし。俺はそれとは違う、自分でもどうなるか判らないような映画が作りたいと思っていて」
――John Cage的な。
「たぶんそう。すごく近いと思います。だからシナリオも、紙1枚に一言書いただけのものなんですよ。“3人、ガレージで制作”とか。そういう大きい括りで撮影をしていて。撮影中は、映画になる、ならない、は考えないようにしてましたね。プロデューサーに“それはやめてくれ”って言われたけど(笑)。何か撮れていれば次はこうしよう、という感じで、その日撮れたものひとつひとつの手触り、匂いを確かめてから、次へ進むように毎日撮影していきました。三富さんがトンネルの向こうに消えていくシーンあるじゃないですか」
――あれすごく良いですよね。
「あれが撮れたから、三富さんが最初に死ぬことになったんですよね(笑)。その場その場っていうと言い方悪いですけど、撮れたものから感じたことで次を決めていくっていう感じで。あらかじめ構築されたものじゃなくて」
――所謂役者を使わなかったのもそういうことですよね。
「そう。だから3人には撮影中、詩人は詩人、画家は画家として生活してもらって。演じてください、っていうんじゃなく」
――いつもと同じってことですよね(笑)。
「そうそう(笑)。だから今回、演出で一番力を注いだのは、“舞台を用意する”ということですね。その上でどうするかは3人に任せて、その設定や場所、意味とか、そういうものを整えるのに専念して」
――台詞が決められているであろうシーンも見受けられますが、そこはどうしてるのでしょうか。
「台詞は、話して欲しい題材だけを伝えて、あとは3人が話し始めて、それが違う方向の行ったとしてもカットをかけないでずっと撮っているんです。3人とは撮影前から結構会って、色んな話をしてたんですよ。とりとめのない話、自分の生い立ちとか。そうやって過ごす時間を、俺は密かにリハーサルだと思っていて。そこで話したことを覚えておいて、撮影の時に“あの話をしてください”っていう感じで。俺が編集をするから、そこで責任を取ればいいや、って思っていました」
――仮に面白い話が出てくるような人物ではなかった場合、成立しなかった撮影ということですよね。
「それはまあ、そうですね。無謀と言えば無謀ですよね」
――この3人だったら大丈夫、という確信はどこから得たのですか?
「なんだろう(笑)。トキちゃん(時政里紗)は一応オーディションていう形で選んだんですけどね。でも俺オーディションなんかしたことないし、なんか“監督っぽい”と思いながら(笑)。それも映画の話は1秒もせずに、生い立ちを1人2時間くらい喋ってもらって。演技が出来る出来ないじゃなくて、好奇心旺盛なところでトキちゃんを選びました。3人を選んだのはたぶん、24時間いつも詩人であり、絵描きであり、音楽家だからなんですよね。俺がいつも映画のこと考えちゃうように。それぞれの作品からそういうものを感じていたんだと思うんですよ。作っているものと人が直結している感じというか。SEPTIMAで演奏してくれる人たちも、そういう人たちばかりな気がしているんですよ。“それしか出来ない”っていうことをやっているというか、不器用というか(笑)。そこからいつも勇気をもらっていて。居心地も良いんですよね。そういう人たちとだったら絶対に何か面白いものが出来る、っていう気持ちがあったんだと思います」
――『Enjoy Your Life』を撮った影響も大きいのでしょうか。
「かなり大きいですね。あれを撮った時に、ツアー中もそうですけど、レコーディングの最中に、この人たち本当にすごいと思って。テニスコーツもJadさんも以前から音楽はもちろん聴いていていて、すごいとは思っていたんですけど、レコーディングを目の当たりにして、同じ空気吸っていいのかな?って思うくらいに感動したんですよ。まあ、さっきの“シナリオは?”っていうのと一緒で、俺もレコーディングというものに対して偏見があったのかもしれないですけど、リハーサルと本番の区別もなく何かやり始めて、良かったらそのまま録っちゃう感じで。“今音楽がここで生まれてまっせ!”っていう感覚をもうビシビシ感じるんですよ。あらかじめ作ってきたものを整えて、っていうんじゃなくて、“今、まさに”という感じ。そういう中で自分も何か作りたいと思ったし、その感覚をずっと味わっていたいというか。あの中にいたら、そのまま消えちゃってもいいや、みたいな感じがありました」
――それを映画でやってみたかった、ということなんですね。
「そうですね。だからガレージでの制作シーンは、3人の中にどれだけ埋没できるかっていうことを考えながらカメラを回しているんですよ。とにかく渦中に、生まれる瞬間に俺も居たい、っていうことだけを考えて」
――そういう部分ではない、後半のホラー要素なんかはやっぱりスト-リーに当てて作ってるわけですよね。三富さんが山口さんに噛み付くシーンとか。
「あれはそうです。 “時間を描く”っていう内容的な部分で外せないシーンだったんですよね。過去、現在、未来の時間が融け合うような映画にしたいっていう漠然とした思いがあると同時に、人も全部融け合う感覚になりたい、っていうのがあるんですよ(笑)」
――割とスピってますね。
「そうなんですよね……。『ドラゴンボール』に出てくるギニュー特選隊の“チェーンジ!”ってあったじゃないですか。小さい頃から、あれすごく良いと思っていて(笑)。こうして喋っている時も、相手から俺を見たらどういう風景なんだろう、とか。24時間俺は俺じゃないですか。そういう絶対的な不自由さに苛つくことがあって」
――肉体の呪縛というか。
「そう。そこから脱したいっていう気持ちがあるんですよね。時間が融け合うのと、主体が融け合うにようなことを願望として持っているから、それを咬んで人が入れ替わることで表現したいと思って」
――ダン・アビーさんと山口さんがオーヴァーラップしたりとか。
「そうそう。鳥取で上映した時に、近くで観ていたおっさんが “ああもう誰が誰かわからん!”て言ってたんですよ(笑)。正しいけど。誰が誰でもいい、みたいな感覚があるんですよね。無我になりたいっていうのはそういうことなんですよ。自我をなくしたいというか。でも絶対無理なわけで。例えば、付き合いたての彼女と夜寝るっていう時に、さっきまであんなに楽しかったのに、寝るのは別々じゃないですか。俺は俺の睡眠しか取れないわけですよね。当たり前なんですけど。どちらかが自分の睡眠を取るためにお互い黙る、その時間が寂しいんですよ。あの孤独感が、人間の孤独感と重なるんですよね、俺は」
――それは本質かもしれないですね。
「そういうことからはもう逃れられないからこそ、解放されたい気持ちも反動となって沸いてくるわけですけど」
――チョウチンアンコウの雄って、雌と出会うと融合して雌の一部位になるらしいんですよ。その瞬間の感覚についてはよく考えますけどね。
「そういう、生物学みたいな話にはすごく興味があって。最近聞いたすごいのは、それも魚なんですけど、雌のお腹の中で孵化した雄が、他の卵に射精して死ぬっていう話で。生殖のためだけに生まれてきて、一度も雌の体の外に出ないで死ぬっていうの聞いて、面白いと思ったと同時にすごく寂しい気持ちになって」
――極論を言えば雌だけで単為生殖できるわけですから、雌雄という事実のためだけに存在するようなものですよね。
「そうなんでしょうね、きっと」
――だから、雌雄、男女というのは、寂しさを生産するだけのシステムである気がしてしまうことがあるわけです。
「本当ですよね。そこからすべてが生まれてますよね……孤独、寂しさっていうのは。そこを踏まえて生きていきたい。俺は(笑)」
――映画のラストシーン、トキちゃんが独りで立ってるっていうのは、そういう意味も込められているのではないかと思ったのですが。寂しさを余韻として残す終わり方ですよね。
「そこまで考えていなかったですけど、そういう風には絶対映ってますよね。あの子だけが時間を超えて、ずっとそこに居続けるっていう。そうかもしれないですね」
――所謂ストーリーテリングの映画とは全く違いますよね。もっとパーソナルな意図というか。
「そう、自分のやりたいこと、思いを込めちゃってる(笑)。だから、この映画が完成しときに、誰が観たいんだ?って思ったんですよ。でも映画って元々軽薄なものだと思ってるから」
――というと?
「だって、わざわざでかい画面ででかい音出して見せるなんて、はったり以外の何物でもないわけで。元来、観ている人をびっくりさせる見世物的な役割もあったわけですよ。俺にとってこの映画は、自分の中でも未解決のものを、どんどん入れて、どんどん提出するっていう、本当に軽薄なものなんですよ」
――でもそれをやったからこそ見えてくるものがあるわけですよね。
「そうですね。投げっ放しと言えば投げっ放しで、自分でも判らないものを提出するけど、お客さんのほうが感じる力が強くて、何か受け取ってくれるだろうっていうところでもあるから」
――“泣ける”みたいな映画ではなくて。
「そうそう。それって結局相手のことを信頼していない気がするんですよね。操るっていうか。変な主従関係だと思うんですよ。細い通路をずっと歩かされて、最後にやっと光を見せられて、みたいな。まあ、そのカタルシスはあるのかもしれないですけど(笑)、俺は息苦しく感じるんですよね。観てくれる人との信頼関係に映画の面白さが宿ることって、あると思うんですよ」
――上映の方法、動き方も、上映→上映終了→パッケージという、その、細い通路のような流れとは異なりますよね。観る側と育てていくというか。
「そうですね、内容的にもそういうものだし。大変だとは思いますけど、それがどう伝わっていくのか、自分の目で確かめていきたいですね」