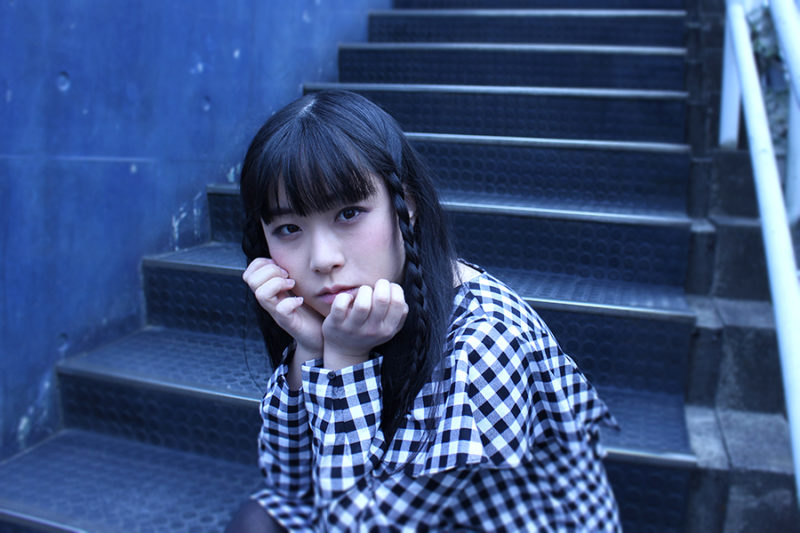今の自分のほうが絶対楽しい
取材・文 | 久保田千史 | 2015年5月
――HighschoolさんはdREADEYEのヴォーカリストでもあるわけですが、活動は別ものとして考えていらっしゃるのでしょうか。
「まあ、必然的に現場の違いとかでそうなりますね(笑)。でも、ライヴの後にDJをやらせてもらうっていうパターンもけっこうありますけど。人とやっているのと、独りでやっているのでは全然違うし。かっこいいものを作りたいというところでは同じですけど。トラックを作るのは、独りっていうのがおもしろいんですよね」
――BBHでは3人での活動ですが、あれはバンドに近い感覚なんですか?
「そうですね。でも、言い方が難しいですけど、BBHのほうが意見を出し合って作っているかもしれない」
――dREADEYEは意見を出し合わないんですか(笑)?
「あはは(笑)。dREADEYEは曲が短いんで。BBHのほうが練り方のスパンがもう少し長いというか。バンドの場合は1曲1曲を淡々と作っていく感じなんですよ。全体を見てアルバムを作るという感覚ではなくて。“作品を作ろう”というよりも“曲を作ろう”みたいなところを意識してるから」
――パワーヴァイオレンスというカテゴリは特にそうかもしれません。パワーヴァイオレンスとヒップホップの間に、共通点を見出しているわけでもなさそうですね。
「そうですね(笑)。共通するものはあまりないかもしれないです。音がデカくてずっしりくるという点では共通している部分があるのかな。エグい感じは、両方で出したいとは思ってますけど」
――例えば、SPAZZのMax Wardさんなんかは、ヒップホップのファンとして知られてますよね。そういうところからの影響はなかったのでしょうか。
「たしかに、SPAZZの2ndとか、彼がその前にやっていたPLUTOCRACYとかって、イントロがヒップホップのトラックだったりするじゃないですか。そういうのはかっこいいと感じていて、僕も作りたいな、とは思ってました。そういう意味では好きですね、SPAZZは」
――あとは、DYSTOPIAのロゴやレタリングがグラフィティっぽいとか……。
「そういう影響はありますよね。1990年代のUS西海岸のバンドって、興味のあることが自分に近い感じがしていたんですよ。クラストみたいに完全に反体制というよりは、楽しみながらやっている感覚というか。そういう感じが強く出てるバンドが好きなんですよね」
――そういう部分で“RAW LIFE”周辺と言われるところと感覚的にリンクしていったのでしょうか。
「“RAW LIFE”はたまたま先輩に誘っていただいて、出させてもらった感じだったので……。何とも言えないですね。やっぱり、世代的に色んな音楽をフツーに聴いてる人が多かったからというのが大きいと思います」
――バンドとトラックメイキング、始められたのはどちらが先だったんですか?
「dREADEYEの前にもバンドやっていたので、バンドのほうが先ですけど、dREADEYEを始めた頃にはすでにトラックを作ってました」
――トラックメイキングに関しては、SEMINISHUKEIの存在が大きかったのでしょうか。
「SEMINISHUKEIと出会う前からトラックは作っていたので、そんなこともないんですよ。最初は“ヒマだからやってみよう”みたいな感じだったのかな(笑)。Anticonとかをよく聴いていて、ラップは別にやりたくないけど、トラックだったら作ってみたいっていう気持ちはどこかしらにありましたけど。こういうのならできるかも、と思って。中学の時からの幼馴染でTac-Rocっていう奴がいて、2人でよくスケボーをやっていたんですけど、そいつが手を骨折してしばらくスケボーができなくなって、すげーヒマだからカセットMTRでも買って何かやってみようってことになったんですよ(笑)。それをしばらく続けていたんですけど、僕のバンドのライヴの時にTacが、自分で録ったやつを勝手に物販に置くようになったんですよ。それに今里さん(aka DJ HOLIDAY / STRUGGLE FOR PRIDE)が反応して、BUSHMINDとかに繋がっていったんですよね」
――きっかけは偶然と言えば偶然だったんですね。
「本当に偶然です(笑)。当時は今みたいに真面目にやろうっていう感覚は全くなかったですね。なんでもかんでもカセットMTRで録音して、くだらないことばかりやっていて。友達に高校の卒業アルバムを見せて、1人1人についてコメントしているのを録ったりとか(笑)。曲はその合間で作っている感じだったんで」
――最初のレコーディングはカセットMTRだったわけですね。Highschoolさんのトラックの少しくぐもった、ザラっとした質感は、その記憶に起因しているのかもしれないですね。
「そうですね。カセットMTRだったらザラついた感じが出せるのかな?とは当初から思っていました」
――最初からPCで制作している方もいらっしゃった世代だと思いますけど、そういう知識の上でのカセットMTRという選択だったんですね。
「一番安いし(笑)。TASCAMのカセットMTRはフォルムも良いんですよね。バンドをやっている人はだいたいカセットMTR持ってますしね。バンドでの録音のスキルがトラックメイキングに繋がっているところはあると思います。まあ、バンドのレコーディングをそのMTRを使ってやったことは一切ないんですけどね(笑)」
――今はどんな機材で制作されているのですか?
「Native InstrumentsのMASCHINEと、シンセで鍵盤弾いたり。あとBOSSのSP-505も使ってます」
――MASCHINEはちょっと値が張りますけど、今もバカみたいに高い機材を使っているわけではないんですね。
「そうですね(笑)。身近なもので、っていう感覚ですね」
――でもたぶん、トリルウェイヴとかもHighschoolさんがカセットMTRで作っていたのと感覚は一緒なんですよね。素材やメディアがネットになっただけで。
「そうなんですよね。だから、SpaceGhostPurrpとかが出てきた時は正直、全然新しいとは思わなかったんですよ。やっとこういうものが認められる時代になったんだな、みたいな(笑)。AnticonとかCOMPANY FLOWのリヴァイヴァルと言える部分もあるけど、今の人たちは見せ方、聴かせ方が圧倒的に上手いですよね。かっこいい」
――今名前が挙がったような人たちは、ヒップホップのフィールドに留まらない支持を獲得していますよね。Highschoolさんのトラックも、ヒップホップとして使われていることが多いにせよ、所謂“ヒップホップ・マナーのトラック”を作ろうとはしていない印象を受けます。
「ヒップホップを作っているという意識はありますけど、“黒いもの”を意識して作るということはないです。黒人になりたいと思っているわけではないんで。それよりも自分が、この東京で生活しているリズムのほうが大事ですね。90年代のサンプリング・ヒップホップも一通りは聴いてきましたけど、そこまで影響は受けてないし、もうちょっと変わったことをやっている人のほうが好きだったんで」
――サンプリングに関して言えば、やっぱりインターネット以降の感触がありますよね。個人的にはNapolianに近いものを感じました。
「サンプリングって、その人が今まで聴いてきたものの表れだと思うんですよ。黒人がソウルをサンプリングするのは、生活の中にソウルがあって、あの曲をここで使ったらおもしろいんじゃないか?っていう感覚だと思うんです。僕もソウルは好きで聴きますけど、それよりも自分が通ってきたもの、身近にあるものをサンプリングするほうが好きですね。そういうマインドがヒップホップなんじゃないかな、って僕は考えていて」
――そうですね。そういう意味では非常にヒップホップです。それが“ザ・ヒップホップ”みたいなものとは別種の質感を伴っているというのはおもしろいですよね。アルバム中最もストレートなヒップホップの「Go Dumb feat. CENJU & ILL-TEE(MidNightMeal Records / MEDULLA, ROCKCRIMAZ)」が異色に響いてしまうという。
「たしかに僕の中でも“Go Dumb”が一番ストレートなヒップホップですね。そういう“黒い”ヒップホップで良いものはもちろんたくさんあるんですよ。でも、それは僕がやらなくても誰かが絶対にもっとかっこいい形で具現化してくれるんで。MASS-HOLE(MidNightMeal Records / MEDULLA)だったり、ISSUGI(MONJU)だったり。そういう中に1人こういう奴がいてもいいんじゃないかな?っていうところですね。同じことをやっても、やっぱり勝てないんで。勝負という面で考えれば」
――BBHの時は“サイケデリック・ヒップホップ”と称されていましたが、単独作ではサイケデリックはサイケデリックでも、どちらかと言えばドリームポップ寄りのサイケデリアという印象を受けました。そのあたりのバランスは意図的に作っているのでしょうか。
「BROADCASTとか、そういうのが好きなんですよ。所謂サイケデリック・ロックのサイケではなくて、90年代インディロックのサイケ感というか。YO LA TENGOもかなり好きです。そういうのはだいたい、嫁の影響なんですけど(笑)。あとはMERCYくんに教えてもらったり。ハードコア・バンドの間でシューゲイザーみたいなのがリヴァイヴァルしてるって」
――NOTHINGとかですか?
「そうですね。WHIRRとか。ちょっと夢見心地な音楽がやっぱり良いですね。Martin Rev(SUICIDE)みたいな音楽も好きです。音色的に、電子音が好きなんですよね」
――「Return Of The Sunset」では8bit音源が使われていますが、あれは何かのゲームの音源ですか?
「それがまさにMartin Revの曲を切り刻んで使っているやつです。何かエフェクトはかけたと思うんですけど、ゲームっぽく聴こえますよね」
――潰れたデジタル音源のリッピングノイズを使っているのも印象的でした。
「ああ~、それはTac-Rocですね。あいつはそういう音で作ってるんです。活動っていう活動はほとんどしていない奴なんですけど、たまにポストにトラック集が入ってるですよ(笑)。ただただ作っているのが好きな奴で」
――フィーチャーされているラッパーの皆さんはどのように選定していったのでしょうか。
「1stなんで、身近にいる人たちというのを意識して選びました。あとは若い人も入れてみたかったから、MERCYくんに紹介してもらった20代前半のJuceとCookie Crunchにもお願いして。彼らはレコーディングとかラップがやりたいっていう意欲がすごくて、刺激的でしたね。ブースから全然出てこないんですよ(笑)。僕らの世代は1回やってみてダメだったら休憩しよう、みたいな感じになるんですけど、JuceとCookie Crunchはちゃんとできていても、さらに少し上を目指すというか。かといって熱い感じというわけでもなくて、当然のことのようにストイックなんですよね。その分スキルも高くて。すごいですよ」
――そうやって下の世代と繋がっていけるのは良いですね。
「音楽をやっていると、そういうことがあるからおもしろいんですよ」
――トラックメイカーだといかがですか?最近、若くて気になる方いらっしゃいますか?
「個人的に好きなのは名古屋のRAMZA。すごいな!と思ったのはQron-Pですね」
――パワーヴァイオレンスではどうですか?
「やっぱりIRON LUNGが圧倒的でしたね」
――でもIRON LUNGは、メンバーのキャリア的にはベテランですよね(笑)。
「そうですね(笑)。でもやっぱり、現行のバンドっていう感じがするから。CAPITALIST CASUALTIESも最近一緒にやったんですけど、ライヴが長くて途中で帰っちゃったんですよ(笑)。IRON LUNGはサクっと終わるんで。醍醐味を感じました」
――日本のバンドだとどうでしょう。
「COMPLETED EXPOSITIONはおもしろいかな。あとはやっぱりFIGHT IT OUTとか……。日本のバンドはそんなに聴かないかもしれないです(笑)。そもそもライヴハウスに行くという行為を、昔に比べるとあまりしなくなっちゃって。行きたいな、って思うライヴがないんですよ。昔はあれもこれもある、っていう感じだったんですけど……。ライヴを観て刺激を受けるのは絶対大切だと思うから、おもしろそうなものがあれば観に行きたいです」
――逆に、トラックメイカーとして、曲を提供してみたい人はいらっしゃいますか?
「おもしろかったら全然、なんでもやりたいですね」
――ヒップホップとは全然違うフィールドの、例えば……アイドルからお話が来たりしたら、やります?
「やりますね。僕別に、アンダーグラウンド志向とか全然ないんですよ。まあ、作る上でどれだけの自由度があるのかにもよりますし、自分が作れないような注文だったら絶対やらないですけど。歌が乗って完成した時に自分でも良いな、って思えるものが100%作れるのであれば、むしろやりたいです」
――アイドルに限らず、Highschoolさんのトラックは歌ものもハマりそうですよね。すごく良さそう。
「実は、今回のアルバムにも本当は歌ものを入れたくて、合いそうな女性の歌い手をMERCYくんと色々探したんですよ。でも……なんというか……アメリカに憧れているのであろうR&Bシンガーか、下北っぽい文学インディポップ路線のどちらかしか見つからないんですよね(笑)。なんか、“ムダなアーティスト感”みたいなものを持ってる人がけっこう多いな、っていう……。その中間で、僕らに近い感覚で音楽をやっている女性っていないのかな?と思ったら絶望的な気分になっちゃって(笑)、止めました。普段着で音楽やってる感じの人がやっぱり好きなんで。仲良くなれるか、なれないかみたいな判断基準もあったし、無理して探すよりも、できることを瞬発力でやったほうが絶対今の自分なんだろうな、と思ったので。合いそうな人がいれば、ぜひ一緒にやりたいですけどね」

――ぴったりの方が見つかると良いですね。しかし、そこまで“ポップ”に対して意識的だとは思いませんでした。
「僕はポップ・ミュージックが音楽として最強だと考えているんですよ。日本て今、音楽の売り上げのほとんどがアイドルじゃないですか。でもそれは付加価値で買われているものが大半で、それって音楽じゃないと思うんです。もっと音楽として見てもらえる環境が作れるのであれば、絶対やったほうが良いと思う。現行のUS、例えばChris Brownとか言ってみりゃアイドルじゃないですか。でも“なんだこのトラック?!”みたいなことをやっているわけで。韓国のアイドルなんかもそうですよね。そういうことができるなら、底上げにも繋がると思うから」
――バンドでやってみようとは思わないんですか?
「それが思わないんですよね。女性のヴォーカルをフィーチャーした、それこそWHIRRみたいなバンドをプロデュースする、とかならやってみたいんですけど。自分ではハードコアのバンド以外は別にやりたいとは思わないです。まあでも、強いて言うなら、Oi!のバンドはやりたい」
――シューゲイザーと全然違いますね(笑)。
「やっぱりスキンヘッド文化が大好きなんですよ。90年代後半のUSスキンヘッズみたいなバンドはやりたいです。DROPKICK MURPHYSとか、憧れもあるし」
――やっぱり、90sがお好きなんですね。
「そうですね……。今でも聴いているようなものに全部出会って、“物心ついた”ような時代なんで。それは絶対、心のどこかには常にありますよね。2000年に入ってからは自分でもバンドを始めていたから、ただただ観たり、ただただ聴いたりして、ひたすら何かに対して悶々としていた頃の感覚に戻ることってもうないじゃないですか。全部止めない限り。童貞の頃の気持ちに戻りたいって思うことがあるのと一緒ですよ。90sは童貞(笑)」
――(笑)。アルバムは全体的にノスタルジックなムードも漂っていますが、それはやっぱり90年代の思い出ということになってくるんでしょうか。
「う~ん、あんまり意識したことはないですけど、そういうことになるのかもしれないですね(笑)」
――かといって、現在を否定するような逃避傾向は全くないです。
「そういうのは全然ないですね。90年代の自分よりも、今の自分のほうが絶対楽しいんで」
DJ Highschool SoundCloud | https://soundcloud.com/dj-highschool