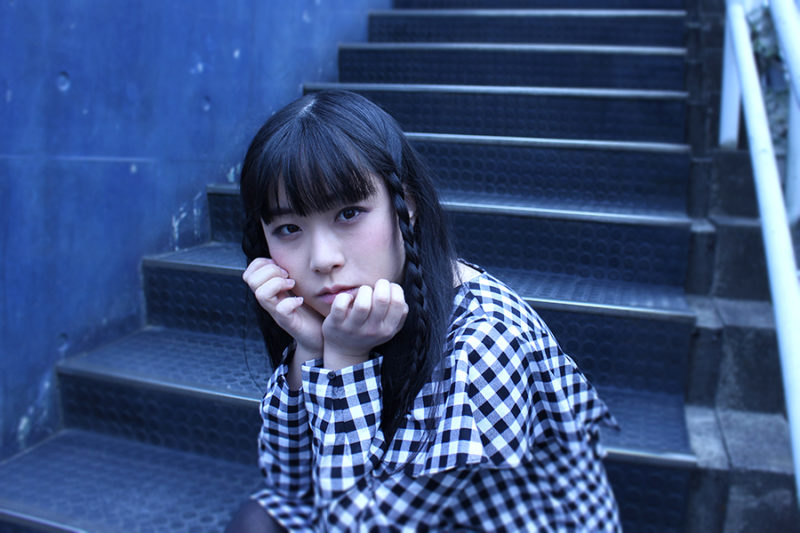前進手段は絶対素手
取材・文 | 久保田千史 | 2013年8月
――さっぱりと音楽遍歴をお聞かせください。ニューウェイヴがお好きだったのでは?という印象を持っているのですが。
「そうですね。大学進学で東京に出て来た1998年頃に、『No New York』の再発があって。それがすごくかっこよくて、そこからいろいろ掘り下げていきました。THIS HEATやTHE POP GROUPは高校生のときに買っていたんですけど、その当時はあまりにも意味がわからなくて(笑)。かっこいいと思えるようになったのは東京に来てからですね」
――他のものも併せて聴くことによって気付いたんですね。
「ようやくわかったんですね。高校生のときは“ブリストル系の元祖がこいつらだ!”みたいな感じで雑誌で紹介されているのを見て買ったんですけど、聴いてみたら全然違ったっていう(笑)」
――では高校生の頃はMASSIVE ATTACKなんかを聴かれていたのですか?
「それが実はあまり聴いていなくて。当時僕は北九州の小倉っていう田舎に住んでいて、周りに音楽友達が全くいなかった上に、高校は2日で行くのを止めてしまったので、3年間友達自体いない生活だったんですよ(笑)。でも音楽は好きだったから、雑誌を見ながらいろいろ聴いていて。その頃ちょうど、 “ラフォーレ原宿小倉”っていう、ヘンにマッシュアップされた名前のビルの中に、タワーレコードが出来たんです。そこに行って試聴したり。情報源がそれしかなかったから、正直言ってMASSIVE ATTCKとかのシブいのはよくわからなかったんですよ。Aphex Twinは“ガキーン!”みたいなところがかっこいいと思っていましたけど」
――“ガキーン!”ていうことは『I Care Because You Do』以降ってことですよね。
「そうですね。ちょうど出た頃でしたね。あとはその時期に出てきたシカゴ音響派みたいなものとか、エレクトロニカ的なものを聴いていました。その後大学に入って、こんな僕にもようやく友達が出来まして(笑)。そこから随分広がりました。DJ Shhhhhがそのときの同級生なんですよ」
――そうなんですね!
「18、9の頃に“Sun Raがすごい”とか“マイブラっていうバンドがヤバいらしい”みたいな話をしていた間柄で。彼から『Loveless』を借りたりしていました(笑)。その頃は彼もDJはやっていなかったし、僕も単なる音楽好きだったんですよね。でも大学卒業以来会っていなくて。“FREEDOMMUNE 0 <ZERO> ONE THOUSAND 2013”(千葉・幕張メッセ)出演時に10年ぶりくらいに会ったんですよ」
――お互い出演者として、その場所で再会するのってすごいですね(笑)。
「……ですね(笑)。彼のDJを聴いて、やっぱりかっこいいな、って思いました。あと大学の先輩に宇波 拓さんがいて、いろいろ教えてもらったりとか」
――だいぶキてるほうに向かってきました(笑)。
「そうですね(笑)」
――土岐さんも現在のようなスタイルになる以前はインプロヴィゼーションの現場にいらっしゃったんですよね。
「はい。即興をやり始めたのも宇波さんの影響が大きかったです。宇波さんのライヴを観に行ったら、ユタカワサキさんが出ていたり、その関連で大友良英さんのライヴに行ったり。いろいろ繋がっていて。その中で“自分も何かやるぜ!”っていう気分になったんですね」
――リスナーとしても、即興ものを中心に聴かれていたのですか?
「その頃はすごく聴いていましたね」
――カセットテープMTRを楽器として使用していらっしゃいましたが、何か参照元や目標があったのでしょうか。
「あまり何かに影響されて、ということはなかったですね。最初はギターだけだったんですけど、カセットテープMTRを併用し始めてからそっちのほうがおもしろくなって、それがメインになったんですよ。おもしろいから使おうと思っただけで、何かになろう、っていうのは全くなかったです」
――そういった即興のシーンから、現在のようなビート・ミュージックに移行していくというのには何かきっかけがあったのですか?
「あの頃って、エレクトロニカと音響派、音響派と即興みたいな感じで、いろんなものがごちゃっと存在してたじゃないですか。自分の中でも、全く同じではないですけど、Aphex Twinと即興のかっこよさってそんなに距離がなかったんですよ。即興って、“どう音を聴くか”みたいな部分で音楽の極北で、すごくハードコアだと思うんですけど。そういう“ハードコア”は様々な当てはめかたがあって、それはビート・ミュージックでも同じなんですよね。それに即興ばかりが好きなわけでもないし、っていうわりと単純な理由から。あとは当時の相方の影響もありますね。最初hanaliって2人組だったんですよ」
――それこそAphex Twin的な(笑)。
「そうそう。もしくはOval的な(笑)。一緒にやってた人が、ガチでDJをやっている人だったんですよね。いつしか独りでやるようになったんですけど、一番最初に石井タカアキ(ラ)くんのOneInchPunch-Labelから出した、cliquetparっていうタイ人とのスプリット7"(『Public Gangsta / Report』2004)のときは2人組だったんです」
――その活動も、即興もしばらく続けられて。
「そうですね。両方をやっていたので、初めてのアルバム(『Spesial Musicu』2009, Telemetry | 大城 真、大谷能生、鈴木康文 aka aen、ユタカワサキなどがゲスト参加)は、hanaliと即興Toki Takumiの2枚組で作ったんですよね」
"forhonpau" from 1st Album 'Spesial Musicu'
――そこから4年の歳月を経て現在に至るわけですが、その間に“ゴルジェ”との出会いが……。クライミングを始められたんですよね。
「はい。4年前の春から山にハマり出して」
――それにはどんなきっかけが?
「完全に漫画の影響ですね。『神々の山嶺』(集英社)っていう、夢枕 獏の小説が原作で、谷口ジローが描いた漫画なんですけど。超感化され易くて(笑)。『岳』も読んではいたんですけど、『神々の山嶺』がおもしろ過ぎていろいろ調べ始めたんですよ。漫画のモデルになった森田 勝とか長谷川恒男について書いた佐瀬 稔のノンフィクションもすごくおもしろくて、 “山には、ここまで人を狂わせるおもしろさがあるんだ”って思ったんです。そういうものに気付いてしまったら、見過ごせないじゃないですか。そうして山に行き始めたら、やっぱりおもしろくて。最初の1年は登山道を登るだけだったんですけど、やっぱりロープを使うような、ハードコアな登山がやりたくなってきて」
――ハードコア癖が(笑)。
「そうなんですよ(笑)。山岳会に入っていろいろ教わったり、沢登りやクライミングを始めたり。おもしろ過ぎて音楽をやる暇がなくなっちゃって(笑)。あれは本当に、みんな言うんですけど、中毒になるんですよね。全く無意味なことを、ひたすらに全力でやるという。それがすごくおもしろくて」
――たしかに無意味っちゃ無意味ですけど……。
「何の意味もないですよ(笑)。見返りなんか絶対ないんですよ。お金もかかるし、疲れるし。むしろ人生にとってはマイナスでしかないです(笑)。それで死にかけたりするのとか本当に意味がない」
――音楽もある種、無意味っちゃ無意味ですけど、通じる部分もあるのでしょうか。
「気が小さいので、音楽をやるときに人のことをすごく意識してしまうんですよ。“どういう風に見えるか”とか“こういう人が聴くんだからこういう風にやらなきゃ”みたいに考えちゃって。本当に自分は“アーティスト”っぽいところはないので。それに対して、山は登る行為自体が全くの自己満足でしかなくて、人を意識するのとは全く違う世界観なんですね。“対人”がないところの楽しさが、“音楽はもういいかな”って思えるくらいで」
――捨てる勢い(笑)。
「そんな勢い(笑)。もちろん音楽はずっと好きでやっていたんですけどね」
――でも、怪我をされたんですよね。
「そう。完全に自分のミスで。非常に恥ずかしいです。もう少し高かったら本当に危なかった。フリークライミングって、ヌンチャクというものにロープをかけながら登るんですけど、それをセットするために上からロープで吊り下げてもらっているときに、ロープが足りなくなって落ちたんですね。登っているときじゃなくて、準備段階でのことだったんですよ。その瞬間は何が起こったのかわからなくて、気付いたら下に背中から落ちている状態でした。3、4mかな。痛いは痛かったんですけど、その後普通に歩いて帰って。途中でちょっとお酒も呑んだりして(笑)。打撲だと思っていたんですけど、検査したら背骨の圧迫骨折で4つ潰れてるから、4ヶ月は絶対安静って言われて。予定は真っ白になり」
――でも不幸中の幸いですよ。音楽だったら、死にかけることはそうそうないと思いますよ。
「そうですね(笑)」
――対人のリスクと、死に隣接するリスク、どちらのほうがリスキー?
「う~ん。でもリスクがないとおもしろくない、っていうは絶対あるんですよね。そのへんは難しいです。“何故山に登るのか”的な話になってくるという(笑)」
――ゴルいですね(笑)。それで4ヶ月もの間、山に登らず。
「そう。そこでまあ、音楽でもやるか……ということで。これを言ったら怒られそうだけど、暇だから(笑)。でも、どうせやるなら前にやっていた感じとはちょっと別なことをやりたかったんです。いろいろ悩みながら試していたんですけど、いまいち確信が持てなくて。自分が何をやっているのか分からない状態というか。じゃあ逆にもう“何をやるか”を決めてしまおう、と思っていた時に、ヘンな曲が出来たんですよ。タムを多用したトラックに、キックを入れ忘れたことで生まれた曲で、それが2ndアルバム(『Gorge is Gorge』2012, GORGE.IN)に入れた“Wide & Gorge”なんですけど、すごく気に入って。これは何ていうジャンルの音楽になるんだろう?って考えていたんですよね」
――その折に出会ったのが“ゴルジェ”の存在だったと。
「そうですね」
――タムの魅力には、かねてから気付いていたのですか?
「逆に、ゴルジェに出会ってからタム好きだったことに気付いた感じですね。例えばMoebius Plank Neumeierの『Zero Set』(1983, Sky Records)がすごく好きなんですけど、あれって“テクノのルーツ”って言われてるじゃないですか。でもキックとスネアじゃないし、テクノではないよな、ってずっと思っていて。タムによって成立しているような音楽は極稀に音楽史の中に現れるんですけど、そういうものを“ゴルジェ”として捉える聴きかたができるようになったんですね。リスナーとしても一種の発見だったんです」
――ある種の音楽をカテゴライズするのではなく、カテゴリ側から音楽を紐付けてゆくという。
「HiBiKi MaMeShiBaさんとも話したんですけど、“キックとスネア”っていうのはやっぱりカルチャーが出てしまうんですよ。キックをどういう音にするか、どう配置するか。それだけでダンス・ミュージックのヒストリーを感じさせるけど、タムだけだとリファレンスとなるものが何もないんですよね(笑)。これはすごく楽だということに気付いて。僕、こう言うとアレなんですけど、“クラブ・ミュージック、コワい”みたいな気持ちがちょっとあって(笑)。そんなにクラブに行くほうでもないし、ブラック・カルチャーに馴染みがあるわけでもないし、ヒップホップみたいにガチでカルチャーとしてやっていこうとしているところには、入って行き辛くて。気が弱いんですよ、本当に」
――上下関係とかもカルチャーとして厳しそうです(笑)。
「そうそう(笑)。何かを踏まえないといけないという部分を切り離して、自由にやれるというのが自分にとって良かったんですよ。裏技的な感じはありますけど」
――ビート・ミュージックの主軸をタムにすることによって、諸々の制約が取り払われたということですね。
「そうですね。作るのがすごく楽になりました」
――そういうところは“GPL” に集約されていますよね。その中で何をするかは作り手に委ねられているわけですし。
「そうですね。結局“タム使え”っていうだけですから。作り手それぞれのものを持ち込めるということは、いろんな人がゴルジェを作るようになって気付いたんですけどね。みんな全く違ったことをやってますから」
――hanaliとしてはディストーション強めなのが特徴のひとつですけど、それもあって、やっぱりちょっとインダストリアルを感じるんですよね。初めてライヴを拝見したとき、トライバルなテイストと相まってTEST DEPTを連想したんです。
「TEST DEPTかっこいいですよね。実は最近初めて聴いて、ゴルいっていうことに気付きました」
――Cut Handsが象徴するように、ダブステップ以降、インダストリアルがに少しずつ復活の兆しを見せている流れについてはどうお考えですか?
「ShackletonとかAndy Stottとかも、ポスト・インダストリアルみたいなこと言われますよね。実はそのへんは全然聴いてなくて(笑)。Shackletonは少しだけ聴いて、かっこいいと思ったんですけど」
――SKULL DISCOの時点でかなりゴルいですよね。
「そうですね。でも、そういう状況があるということは全く知らなかったんですよね……。自分はたまたま怪我をして始めただけで(笑)。ただ、その流れのおかげでリスナーに素直に受け止めてもらえる、っていうのはあるかもしれないですね」
――同時多発的に感覚を共有するのって音楽の不思議ですよね。
「おもしろいですよね。でも繋がることはいろいろあって。DJ Shhhhhもそうなんですけど、Goth-Tradさんと“Back To Chill”をやっているDJ百窓(DJ100mado)って、昔はBusRatch(毛利 桂、山本隆博を中心とするターンテーブル・インプロヴァイゼイション・コレクティヴ)で即興をやっていて、よく一緒にライヴやっていたんですよ。うちの実家に泊まってもらったこともあったり(笑)。しばらくして『Grime』(2004)がRephrexから出た頃に彼はドラムンベースのDJを始めて。当時百窓くんとは中二なことばかり話してたんですけど(笑)、今となってはすごいDJになって、一緒にイベントに出たりして」
――土岐さんだって、今年は「FREEDOMMUNE」に出演されて。お客さん、たくさん踊っていらっしゃいましたよ。
「びっくりしましたね。本当に、ホッとしましたよ(笑)」
――宇川(直宏)さんがきゃりーぱみゅぱみゅさんの楽曲「み」(2013『なんだこれくしょん』収録曲)について、ゴルジェとして言及されていたのはご覧になりましたか?
「見ました(笑)」
――きゃりーさんの該当楽曲は聴かれました?
「それがまだ、最初の1分くらいしかちゃんと聴いてないんですよ……」
――あの曲の歌詞に “ぱなり ぱなり”という一節があって、中田(ヤスタカ)氏が暗にhanaliを匂わせているのでは?と勘ぐりました(笑)。
「まじっすか(笑)。そうだったらすごいですけど、全くそういう情報は入ってきてないですね、残念ながら」
――EYƎさん(山塚アイ)もゴルジェがお好きなようですが、直接やりとりされているのですか?
「それが、ないんですよ。以前、東京・四谷 OUTBREAKで開催されている“GHETTO VALLEY!!!!”というイベントに出たとき、たまたま来ていたEYƎさんがライヴを観てくださったらしくて。そのことをMOODMANさんや宇川さんにお話しされたみたいなんですよ。それでMOODMANさんもDOMMUNEで最初にやったときに観に来てくださって。意外なところで繋がっていくんだな、って思いました」
――“BOA DRUM”はかなり感覚的に近いものありますよね。
「もう、ゴルいですよね。ドラムがバカスカ鳴ってるときのかっこよさって、あまりモードや時代に左右されないものですよね。そこに焦点を絞るジャンルとしてゴルジェがあってもいいんじゃないかな、と思いますし」
――TRAXMANの来日公演にも出演されましたが、あれにはどういった経緯で?
「Booty TuneのD.J.Aprilさんが、去年の夏にコンピレーションを出してすぐの頃にメールをくれて、その流れで呼んでくれました」
――ゴルジェって、ジューク / フットワーク方面からの人気が高そうですよね。
「どうなんですかね(笑)。でも、Aprilさんはシカゴのカルチャーにすごく造詣が深い人なんですけど、そこに全く囚われてはいないんですよね。D.J.Kuroki KouichiさんやD.J.Fulltonoさんも同じで、ジュークの人たちってジャンルや派閥は関係なく、おもしろいものはおもしろいっていう感覚があると思うんですよ。でも本当のところ、今だに何で呼ばれるのかよくわからないんです(笑)。でも呼んでいただけるのはすごく嬉しいです」
――う~ん、ダンス・ミュージックという意識でやられているわけではないんですものね。共通点は感じますけど。
「そうですね。やっぱりネットが大きいですね。ジューク、特に日本のジュークって、そもそもあまりフィジカルのリリースもないし、作ったものを即ネットで届けて、すぐに次、っていう感じじゃないですか。ゴルジェもそうなんですよね。そういう状況って、僕が山に行き始める前と全然違いますね」
――諸々議論はあるでしょうけど、楽しいですよね。
「そうなんですよね」
――かといって現場のことを考えていなかったり、戦略に終始しているわけではないんですよね。
「やっぱり、音楽ありきですからね、絶対。“ゴルジェ”と言ったらゴルジェになるという、雑なジャンルですけど(笑)。そういう異物感を、いろんな人がおもしろがってくれる状況は楽しいです。ノイズの人からも反響があって。Government Alpha(吉田恭淑)はバロムワン名義で“GHETTO VALLEY!!!!”に出ているので、よく話すんですけど、こういうやりかたもあったんだ、っていう感じで反応してくれて。自分には才能と呼べるものがほとんどないという確信はあって、逆に自分に才能があると勘違いして後々辛くなるのという経験はいろいろしたので(笑)、野心は全くなかったんですけど、おもしろいと思ってやったことに対して反応があるのは嬉しいですね」
――そういうゴルジェの自由な感覚は、山に出会ったときの気持ちと通じる部分があるのでしょうか。
「そうですね。ひとつ、自分の中で“フリークライミング”を基準としているところがあって。“フリー”って “素手で”っていう意味なんですよ。フリークライミングが出てくる背景にエイドクライミングっていう登りかたがあったんですけど、それはハーケンを打ち込んでそこにアブミっていう梯子を付けたり、ボルト打ち込んだりして登るスタイルで、それによってあらゆるところが登られて停滞した時期があったんです。それに対して素手で登らなければ意味がない、ということで、アンチを唱える連中が生み出したのがフリークライミング。ボルトは墜落時の対策でしか使わないで、前進手段は絶対素手っていうルールを作ったんです。ちょうどプログレとパンクみたいな関係ですね。クライミングのテクニックはフリークライミングから発展したものが多いんですよ。ゴルジェは、素手で、手探りでやるっていう、まあパンク的DIYみたいな、そういうイメージなんですよね(笑)。何かのカルチャーを利用しないっていう。そういうルールの下に、山とか壁とかを見たときに感じるかっこよさと同じ感覚の音楽があればいいな、っていうモチベーションで成り立ってますね」
――すごく直感的なものなんですね。
「そうですね。自分が作って、聴いて、かっこいいと思える、そこだけをシンプルに目指そうという。さっきの登山の話と一緒で、音楽に対しては、もう見返りを求めないと完全に決めているんで。プロでやっている人は絶対にそこを求めないといけないから、悪いとは全然思ってなくて、むしろ本当にすごいことだと思うんです。でも僕はどうせ作るんだったら人とは違うものを作っていたほうが絶対楽しいし、それ対して起こる何かについては、もう期待しない。“アーティスティック”とかそういうことじゃなくて、ただ自分が長く続けるためにどうやればいいかいろいろ悩んだ結果なんです。本当に気が小さいんで、ビクビクしてるんですよ(笑)。いかにして自分を傷つけずに長く続けるか、というところでバランスを取って」
――続けることの意味は大きいですよね。
「ですよね。続けるのって、やっぱり大事なんですよ」
 ■ 2013年9月25日(水)発売
■ 2013年9月25日(水)発売
hanali
『Rock Music』
Terminal Explosion
CD TEXTCD-006 1,400円 + 税
https://terminalexplosion.bandcamp.com/album/rock-music
[収録曲]
01. We need
02. Rebolted Wonder Gorge Ensemble Band
03. Stop The Night Boldering in Kawai
04. Gorge in to out (Variation)
05. GODGE
06. Hang The Gorge Bootists
07. Survival something
08. The Mytery of Gorge
09. Too Static, Too Dynamic
10. Gazz
11. Harder or Hardness (Variation)