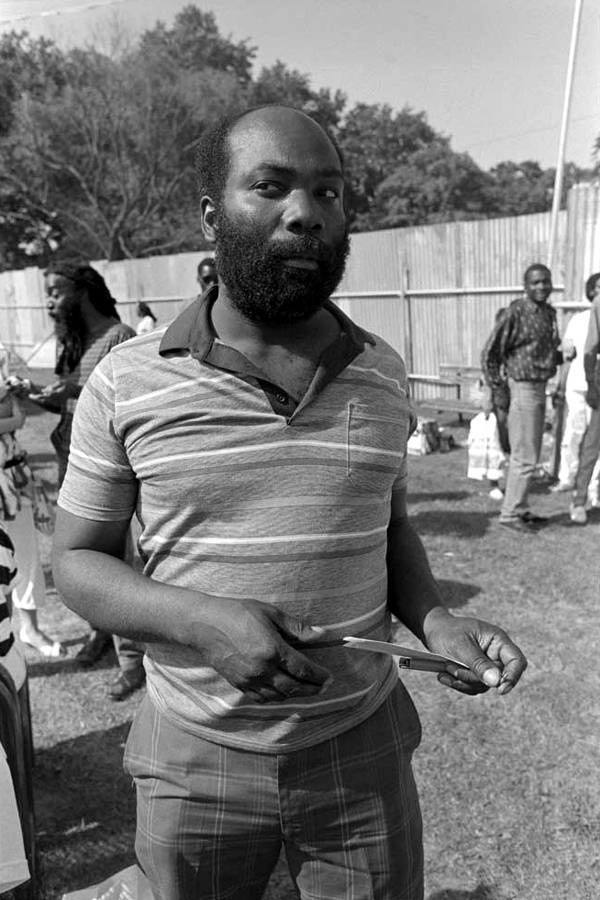おもしろそうだったら断れない
取材・文 | 久保田千史 | 2012年7月
翻訳 | 浜本啓佑
――首の手術をされたとのことですが、どんな病状だったのですか?
「ステージで倒れて、風呂でも倒れて、右手の指が動かなくなったんだ。その麻痺の原因だった首の神経を治すために手術をしたよ」
――術後の経過はいかがですか?もうベースは弾ける?
「今はまた弾いているよ」
――今回の作品の元となっている70~80年代の作品は、これまで聴き直したことはなかったのでしょうか。再び聴いてみて、どう思われましたか?
「アルバムのミックスをするまでは、聴き直さなかったね。この作品がなかなか良いって気づいたのは、Mad Professorのスタジオでマスターテープができてからだよ」
――I Royをはじめ、Style Scott、ASWADの面々など、プレイヤー陣が豪華ですよね。彼らとの、録音当時のエピソードがあれば教えてください。
「ひとつ覚えているのは、Angus Gaye(ASWAD)が“Afreecan”でドラム・ソロを録ったときかな。どんなサウンドになるか気になったから、あまり期待せずにとりあえず録音したんだけど、聴いてみたら完璧だったんだ」
――そもそも、こんなに素晴らしい楽曲群なのに、なぜ未完成のまま放置されることになってしまったのですか?
「リリースされなかったのは、当時手がけていたプロジェクトが多すぎたからだね」
――この作品に使用されている最も古い音源は1978年録音とのことですが、同年にはBlackbeard名義での初ダブ・アルバム『Strictly Dub Wize』をリリースされていますし、MATUMBIのデビュー作『Seven Seals』やLinton Kwesi Johnsonのエポックメイキングな作品『Dread Beat An’ Blood』も78年に発売されています。なぜそんなにハードワーキンだったのですか?やってみたいことがたくさんあったのでしょうか。
「色んなユニークな人たちから仕事のオファーが入ってきて、おもしろそうだったから断れなかったのかな。だから、ほとんど常にスタジオに入ってた。やるべきプロジェクトがいっぱいあったんだ。今回のアルバムは78年に録音されたものもあれば、79年に録音されたもの、Fela Kuti、坂本龍一、Janet Kay、THE BOOMTOWN RATS、Linton Kwesi Johnson、BANANARAMA、THOMPSON TWINS、Edwyn Collins(ORANGE JUICE)といったアーティストのレコーディングをしたStudio 80を建てた80年に録音したのもあるよ」
――例えば“ダブの誕生”のような革新には、録音技術の進化が欠かせなかったと思います。今回Ariwaで最新機材を用いて作業してみて、技術的に当時と違うと感じたところはありますか?
「データを2inchのアナログ・テープからデジタル・ハード・ドライヴへ移して、音質が変わらなかったときは感動したよ。デジタルとアナログのアウトボードが良い具合に混ざり合うと、昔夢見たようなエフェクトが得られたんだ。あと、各チャンネルに個別でエフェクトをかけてもまだチャンネルが余ってるのも助かったな」
――70~80年代は、あなたにとっても、レゲエにとっても、激動の時代だったと思います。当時のあなたにとって、ジャマイカン・ミュージックはどんな存在でしたか?
「70年代、ジャマイカン・ミュージックは俺のすべてだった。リラックスするときも聴いていたし、作曲をするときもレゲエのビートを使ってたしね」
――80年代のニューウェイヴ期には、レゲエだけでなく、THE POP GROUP、THE SLITSからORANGE JUICE、坂本龍一まで、様々なアーティストの作品に携わっていますよね。それは単にエンジニアとしての興味だったでしょうか。それとも音楽的に変化を求めたのですか?
「俺がニューウェイヴ期に様々なタイプのアーティストと関わってたのは、あらゆるスタイルの作曲、録音、ミックスができるようになりたかったからだよ。その結果俺は、初めて英国でダブ・アルバムをリリースするサウンド・エンジニアになって、坂本龍一の『B-2 Unit』に入っている“Riot in Lagos”にダブのミックスを加えることもできた。THE POP GROUPやTHE SLITSに関しても同じだよ」
――現在、レゲエは多種多様な姿となって受け継がれています。70、80年代当時のあなたが、レゲエの末裔にあたる今の音楽を聴いたらどう思ったでしょう。
「現在のレゲエ・ミュージックを当時の自分が聴いたら、今の自分と同じ感想を持つと思う。俺の好みからすると、機械的で固く、暖かみが足りないんだ」
――あなたの名作アルバムのタイトルをバンド名に冠する、日本のダブ・バンドについてどう考えていますか?
「AUDIO ACTIVEは刺激的なバンドだよね。自分のアルバムのタイトルをバンド名にしてもらえて名誉だよ。少し前に、彼らのステージのライヴ・ダブ・ミキシングをやったんだけど、ヘヴィで最高だったなあ」
――Pressure Soundsからのリリースは編集盤『Decibel』以来2度目ですよね。同レーベルは良質なリリースばかりですが、その中からあなたのお気に入りの作品を教えてください。
「Pressure Soundsのリリースから5つだけ選ぶのは不可能だね。彼らは長年、俺の好きなアーティストの作品をたくさんリリースしてきたんだから。Pressure Soundsの作品は全部好きだし、彼らのカタログに自分の作品が入っていることを誇りに思うよ」
Pressure Sounds Official Site | https://www.pressure.co.uk/