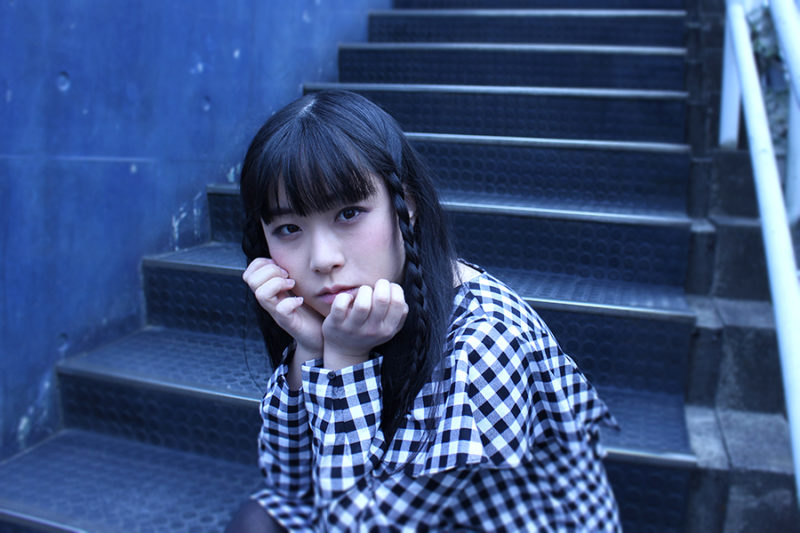On-U Sound 30th Anniversary
取材・文 | 久保田千史 | 2011年12月
通訳 | 原口美穂
Main Photo | ©Tadamasa Iguchi 井口忠正
――30年前にOn-U Soundをスタートさせた時、レーベルの基本理念のようなものはあったのでしょうか。
「正直言ってそういうのは全然なかったんだ。レーベルとして生き残っていければいい、っていう気持ちだけで」
――最初から“レゲエのレーベル”として始められたのですか?
「最初はそうじゃなかった。一番最初にLPをリリースしたNEW AGE STEPPERSは厳密に言えばレゲエではなかったし、2枚目に出したTHE MOTHMEN……このアルバム(『Pay Attention』1981)は激レアだよ……後にSIMPLY REDになるバンドなんだけど、それも全然レゲエを演奏してはいなかった。“レゲエとはちょっと違ったものを出すレーベル”といったところかな。意図的にそうしたわけではないんだけど、On-Uの前にレゲエのレーベルはすでにやっていたからね。“4D Rhythms”っていうレーベルで、CREATION REBELの『Starship Africa』1枚しか出していないんだけど。“Hitrun”ていうレーベルもやっていたし」
――NEW AGE STEPPERSが出てきた頃は“ニューウェイヴ真っ只中”という感じだったと思います。その環境にあって、Sherwoodさんはどんな音楽を聴かれていたのですか?
「その頃からずっとレゲエ・ヘッドだよ。周りにいたTHE POP GROUP、Mark E. SmithのTHE FALLとか、そういうものは全部聴いてはいたんだけど、どれかにものすごくハマるっていうことはなくて。特に好きで聴いているものと言えばやっぱりレゲエだったよ。その頃一緒にツアーを回っていたのもTHE SLITSやTHE CLASHで、レゲエに近いものだったしね」
――レゲエに造詣の深いSherwoodさんには、周りの“レゲエ・フレイヴァ”なバンドはどう見えていたのでしょうか。
「おもしろかったよ。最初の頃の、黒人たちが育ててきた第1、第2世代のスカやレゲエなんて、昔はレコード屋の隅っこで安売りされているような、言ってしまえば二流の存在だったんだ。初めが小さなものだっただけに、それが突然大きなものになってゆくのを見るのはおもしろかった」
――レゲエが大きな存在となるにあたり、やはりパンクの影響は大きかったのでしょうか。
「UKレゲエにおいてはそうだろうね。それまで白人と黒人が同じステージで演奏するなんていうことはなかったんだけど、Bob MarleyやTHE CLASH、THE RUTS……THE RUTSはすごく大事なバンドだよ……彼らが出てきてからはそういうことはなくなったんだ。THE CLASH、THE RUTSはレゲエのフレイヴァがあるバンドだったけど、SEX PISTOLSのJohnny Rottenだってレゲエが大好きだった。SEX PISTOLSが解散した後に結成したPiLを見れば分かるでしょ?当時のUKでは“Rock Against Racism”や“Legalise Cannabis Campaign”みたいにポリティカルな運動も多くて、一緒になって盛り上がっていったんだよね」
――On-Uのカタログを見ていると、ニューウェイヴィなリリースと、ルーツ寄りなリリースと2パターンありますけど、これも意図的にやったことではないんですか?
「全く意識はしていなかったんだけど、僕はプロデューサーだからさ、様々なエリアのアーティストと出会う機会があって、みんながいろんなヴァイブスを持ち込んでくれたんだ。例えばPiLのKeith Levinはすごく良いギタリストでしょ?だから僕のレゲエのトラックでギターを弾いてもらおう、っていう風に。そうやってセッションを繰り返して、いろんなものをミックスしながらスタイルを作っていったんだ。すごくおもしろい作業だったよ」
――素朴な質問ですけど、そうやってレーベルを続けてゆく中で苦労したのはどんなことですか?
「みんなから期待されるのがキツかったなあ。アーティストたちは“もっと売りたい”っていう思いを持っていたんだけど、アンダーグラウンドでやっていたから、なかなか応えられなくてね。そういうときは本当に悲しかったよ(苦笑)」
――今でも、制作はもちろん、発送などの作業もご自身でやられているんですよね。
「始めたばかりの頃は5、6人でやっていてね。前にやっていたレーベルの頃から引きずっていた借金の問題もあったりさ。Kishi(Yamamoto)がアートワークやビジネス周りをしっかりやってくれていたから、すごく助かってた。最初の3年間はすごく大変だったけど、だんだん軌道に乗ってきたんだ。そうなってくると、もっとレコードを出せっていう話になるんだけど、なかなかそうもいかなくてね。でも“もっと良くなるはず”っていう思いは持ち続けていたから、良いアーティスト、作品を続けて送り出すことができたんだと思う」
――“もっと良くなるはず”という信念はどんなところから得られたものだったんですか?
「“隣の芝は青く見える”って言うけど、僕は売り上げのことは気にしていなかったし、十分良いっていうことはわかってたからさ。金銭面でみんなからの期待に応えられないのはツラかったけど、“素晴らしいものをリリースしているんだ”っていう思いは変わらなかったから」

――レゲエ / ダブと接した仕事の傍ら、エンジニアとしてSKINNY PUPPYやMINISTRY、KMFDM、NINE INCH NAILSをはじめとするエレクトロニック・ボディ・ミュージックや、DEPECHE MODEなどのミックスも手がけていらっしゃいますよね。そういったアーティストたちとレゲエってすぐに結びつかない気がするのですが、どういった経緯で手がけることになったのですか?
「MINISTRYのAlain Jourgensenとか、DEPECHE MODEのプロデュースをしていたDaniel Millerは、僕のところまで来て“一緒にやりたい”と言ってくれたから、引き受けることにしたんだ。レゲエだけに留まらないで、どんどんチャレンジしていきたい気持ちもあったから、おもしろそうだと思って」
――音楽的には?好きでしたか?
「うん、好きだよ。でも家でじっくり聴くほど好きかって聞かれたらノーだな。こういう場では正直に言わないとダメでしょ(笑)?」
――(笑)。僕はSherwoodさんが手がけたEBMの作品が大好きです。特にMINISTRYの『Twitch』は、イカれたテープ・ワークや変態的なパニングなど、On-U印のミキシングがエクストリームに現出した作品だと思うんです。ああいうミキシングはどうやって編み出していったのでしょうか。
「それはMark Stewartと一緒に作っていった。エクストリームにミックスする術は彼から学んだんだよ」
――でも本当は、もっとルーツ・レゲエ寄りのサウンドがお好きなんですよね?
「そんなことないよ。ジャズやブルーズ、マイナーコードでダークなものは大抵好きだよ。レゲエ / ダブでも、特にメランコリックで哀しげなのが好きだね。ムーディで歌詞も素晴らしいとなお良い。今一番良い例を挙げるとLittle Axe(Skip McDonald)の『If You Want Loyalty Buy A Dog』みたいなね」
――あのアルバム最高でした。
「でしょ!? ルーツ・レゲエ + ブルーズっていう感じでマイナーコード満載で最高に美しいんだ。ブルーズが好きな人はブルーズじゃないって言うかもしれないし、ルーツ・レゲエが好きな人はブルーズ過ぎるって言うかもしれないけど、僕にとっては完璧なバランス。レゲエだけ、ブルーズだけ、っていうのはあまり好きじゃなくてね。そこにチャレンジが入っていないと新しいものが生まれないと思うし」
――レーベルを始めた頃も、ダブはフューチャー・ミュージックを作り出すためツールのひとつだったのではないでしょうか。
「始めた頃はそんなこと全然考えてなかったよ(笑)。でも作品を作っていくうちに、新しいものを作るほうが楽しいってだんだん思うようになっていったんだ。今も自分の新しいソロ・アルバム(『Survival & Resistance』)を作っているところなんだけど、それも音にいろんなスパイスが入っていて、ただダブなだけじゃないんだ。今までで一番自分らしい作品だと思う」
――様々な要素を吸収して進化を続けるのはOn-Uの大きな特徴でもありますよね。NEW AGE STEPPERSの最新作『Love Forever』もモダンで、それを象徴していると思います。
「『Love Forever』聴いてくれたの?」
――もちろん。素晴らしかったです。
「よかった!ありがとう」

――レゲエの進化のひとつに、ダブステップが挙げられますよね。ダブステップ以降、レゲエに対する注目度が再び高まっているように思うのですが、いかがですか?
「そうだといいなって思うよ。ダブステップは最高の進化型のひとつだからね。でも、ひとつ問題なのは、その裏側でジャマイカのレゲエが死に絶えつつあるっていうこと。新しいSly & Robbie、若いプレイヤーが全く出てこないんだ。ダブステップは素晴らしいけど、同時に本物のレゲエが消えてゆく傾向にあるから、僕はその火を消さないってことを目標にしているよ」
――On-Uとして、具体的に行っている策などはあるのですか?
「そうだね、古いスタイルの作品でも新鮮に聴こえるようにいつも心がけてるよ。本物のレゲエにもちゃんと目が向くようにね。それから若い人たちと作業しながら、ひとつひとつ質の高いものを作ってゆくこと。才能ある若者はたくさんいるから、そこに僕たちの持っている知識をミックスするのは大切なことだと思うんだ」
――今、ジャマイカの若いアーティストでお気に入りはいますか?
「ほとんどいない。TURBULENCEとかは好きだけど。今のジャマイカはヒップホップ・フレイヴァが入り過ぎてしまっているし、CDプレイヤーも持っていないようなデジタル世代が音楽そのものを大切にしていないんだよね。ジャマイカには今、国の中にレコード・ショップが2軒くらいしかないし。素晴らしいミュージシャンはたくさんいるんだけど、その才能が活かせる方向に向かっていないように見えるんだ。悲しいことだよ」
――では、現在良質なレゲエを産出する国というと?
「イングランド。日本にも良いレゲエのミュージシャンがいることは知ってるでしょ?ドイツにもGENTLEMANみたいに優れたアーティストがいる。イタリアやフランス、ポーランドにもね。今では世界中にコミュニティがある。そうなったのはBob Marleyの普遍的な良い歌詞のお陰だろうね。ジャマイカではどんどん衰退しているけれど、世界的に見たら、もしかすると今が一番レゲエが愛されている時代なのかもしれないな、とも思うよ」
――難しいですね。
「そうだね。でも、メントの時代から、スカ、ロックステディ、レゲエ、ダンスホール、ダブ、今のダブステップに至るまで、それぞれブームが続くっていうことはないわけじゃない?そうやってパーツが換わっても、全く変化しない部分がある音楽っていうのはやっぱりすごいよ」
――レゲエの変革と共に歩んで30年間、レーベルを続けていて良かったことは?
「う~ん、何かひとつ思い出みたいなかたちで“良かった”と思うことはないかな。30年間、良かったことは常にたくさんあって、それが全部繋がっている感じ。例えば“あのレコードが好き”って言ってもらえたり、パーティでみんなが楽しそうにしているのを見られたり。そういうこと全部。オカンに“ちゃんとした仕事に就け”って呆れられながら続けてきた甲斐があるってもんだよ(笑)。オカンはDEPECHE MODEのレコードが売れたときですらそんな感じだったんだ(笑)。僕自身は特に金持ちになったわけじゃないけどさ、みんなが敬意を払ってくれているのも、楽しんでくれているのも、いつも感じてるから。やっていて良かったのはそういうことだよ」